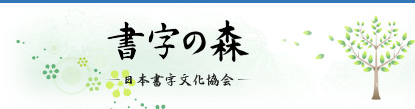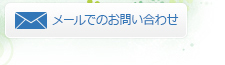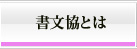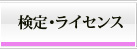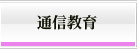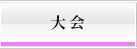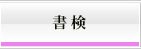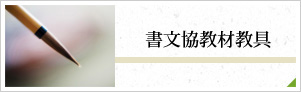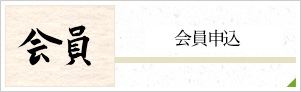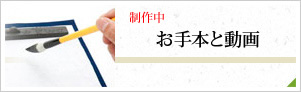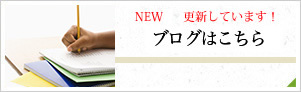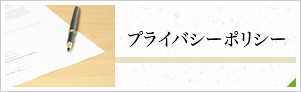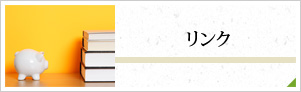|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||

|
*用紙は書文協作成応募用紙あるいは日本郵便はがき使用(実施要項参照) §書き初め展覧会§
指定課題の用紙は、幼年〜小2は半紙、小3〜中3は八ツ切、高校・大学生は半切です。(他自由課題の用紙等、実施要項を参照) HOME
| 書文協とは?
| 検定・ライセンス取得
| 通信教育
| アクセス
| 大会
| 各種ダウンロード
| リンク | ||||||||||||||||